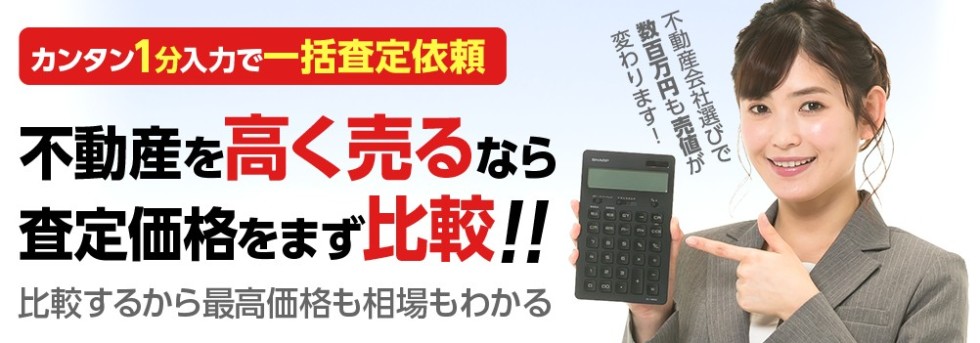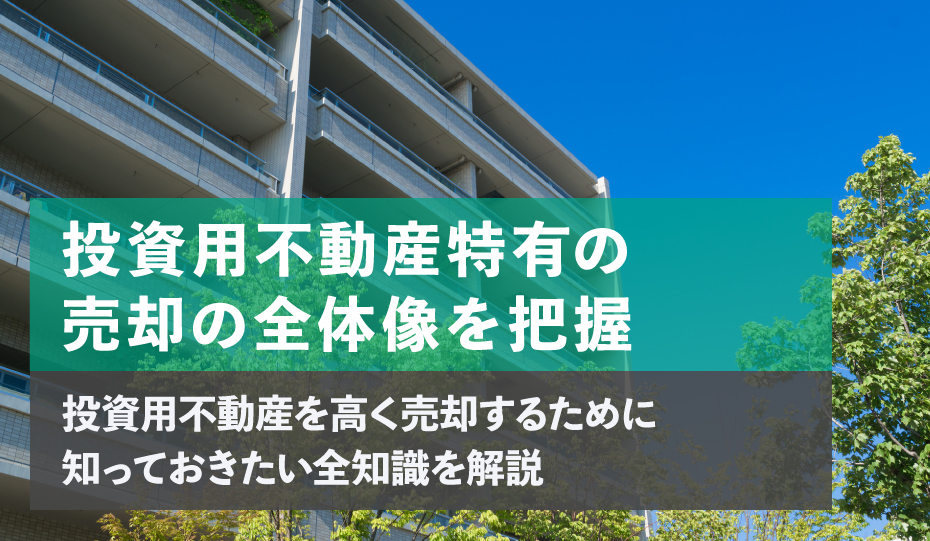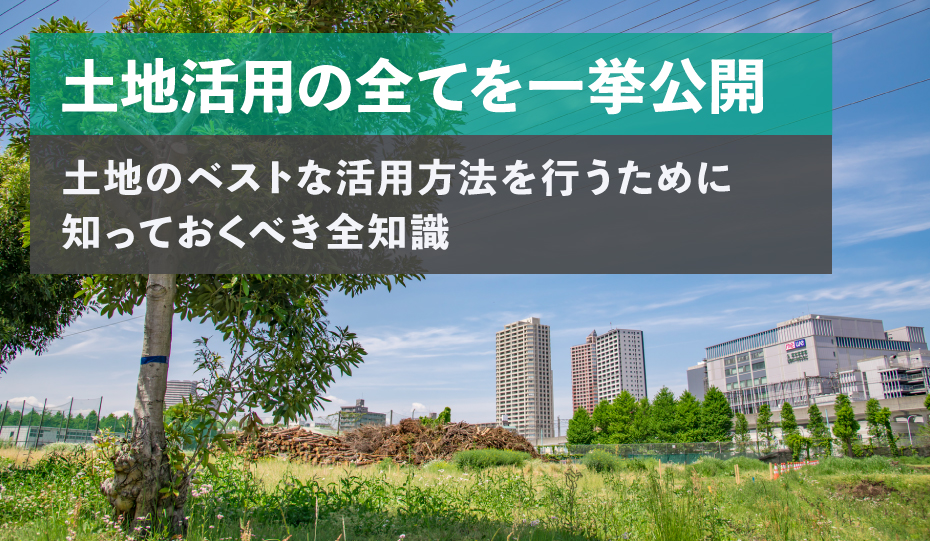不動産売却– category –
-

傾斜地・がけ地・造成地の売却は苦戦する!おすすめの業者や活用方法は?
-

不動産売却のクーリングオフはできる?適応・適応外の基準を徹底解説
-
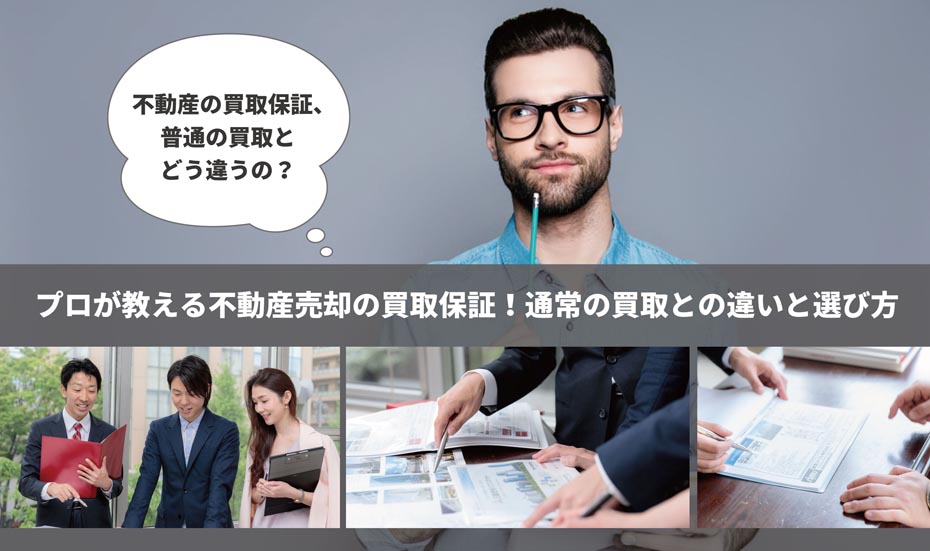
不動産売却の買取保証とは?通常の買取との違いについて
-

認知症になってしまった親の不動産を代理で売却する方法と注意点
-
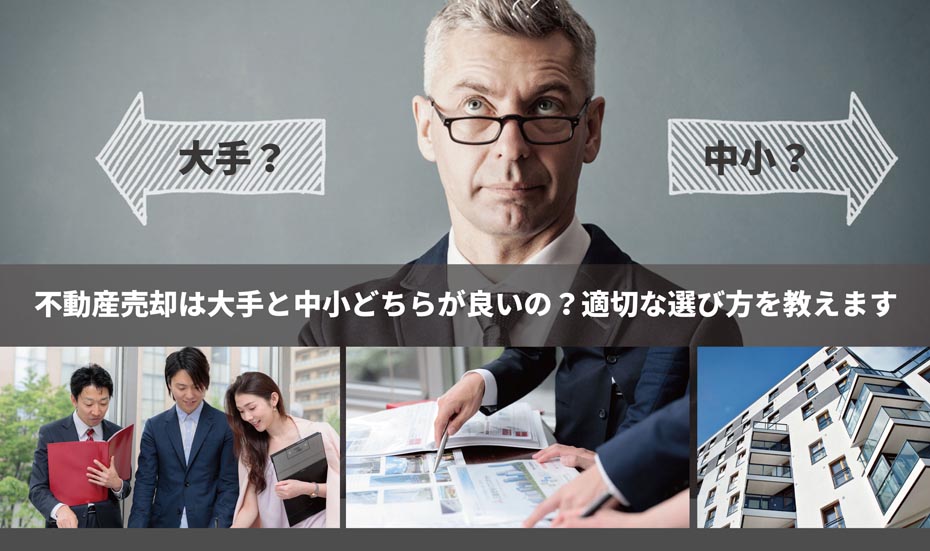
不動産売却は大手企業と地元などの中小企業どちらが良い?それぞれのメリット・デメリット
-

遠方や遠隔地の不動産の売却はどうすればいいの?ベストな方法を徹底解説
-

不動産売却の登記費用はどれぐらいかかるの?売主・買主はどちらが負担?
-

不動産売却するときに住民票は必要なの?売却後に住民票を移すタイミングは?
-

不動産買取でよく起きるトラブル内容と回避方法
-

一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の特徴とそれぞれの違い
-
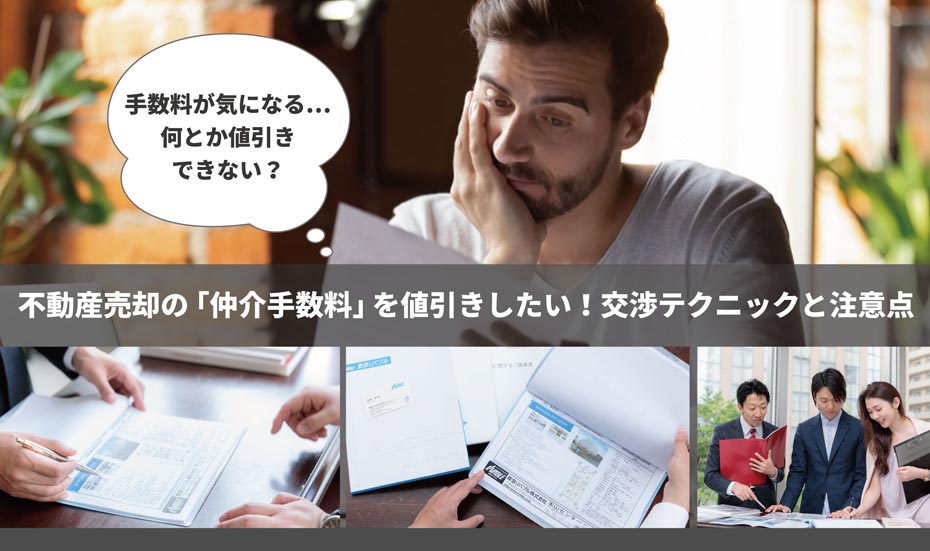
不動産売却の「仲介手数料」を値引きしたい!交渉テクニックと注意点
-
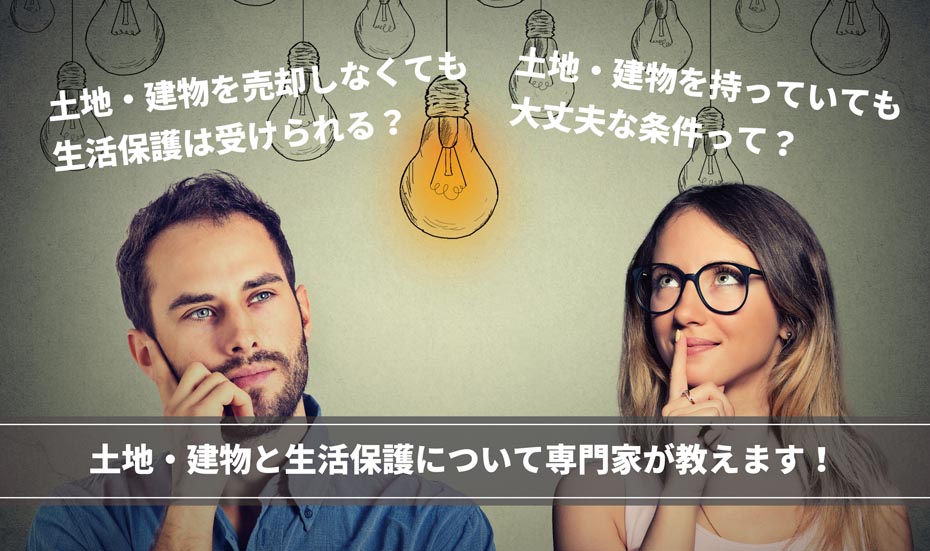
生活保護を受けるために所有している土地や持ち家は売却必須?固定資産税の扱いは?
-

不動産売却した後に営業マンへお礼は必要?渡すタイミングはいつ?
-
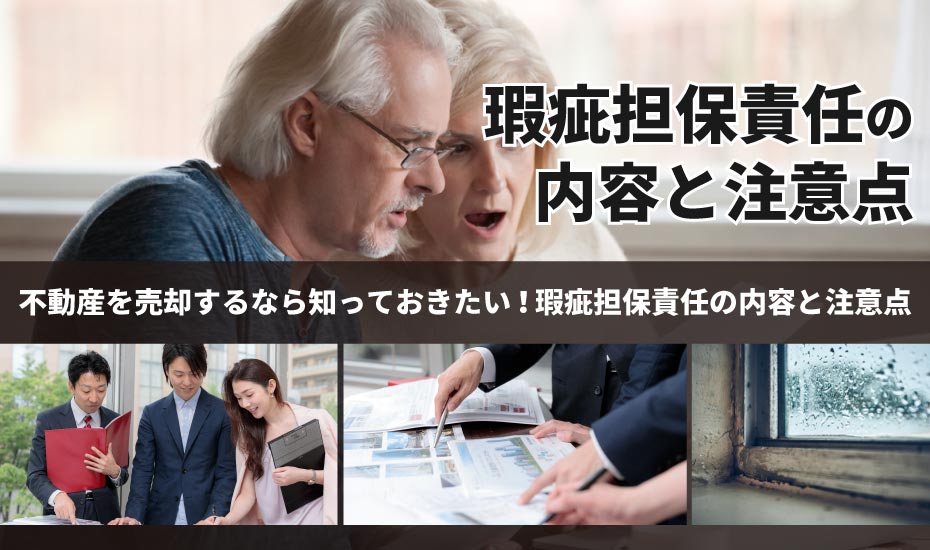
不動産を売却するなら知っておきたい瑕疵担保責任の内容と注意点
-

不動産売却したら介護保険料は値上がりする?条件とお得な税金特例